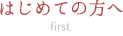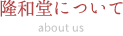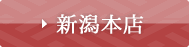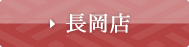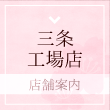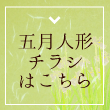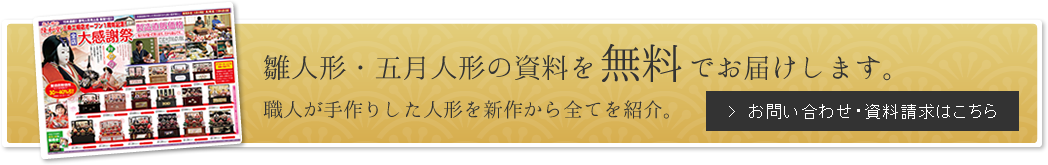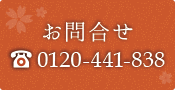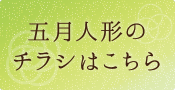昔から「一夜飾りは縁起が悪い」と言い、前日になって慌てて飾るのはタブーとされています。それでなくともお節句が終わり次第片付けるのですから、お子様のためにも早目に飾って華やかなお節句気分を盛り上げたいものです。
◆雛人形は旧暦でお祝いする地域もありますが、節分で豆まきをして厄を払った後の立春から雨水(毎年2/18前後)の間に飾るのが一般的です。
また、雨水に雛人形を飾ると、良縁に恵まれるという言い伝えもあります。
「良縁なんて早すぎる!」とパパやお祖父ちゃんの声が聞こえてきそうですが、良縁とは結婚のことだけでなく、様々な人や物事と縁を結ぶことです。縁起のいい言い伝えは取り入れてもいいかもしれませんね。
昔はよく言われた『雛人形の片付けが遅いと婚期が遅れる』というのは迷信で、簡単に言えば「お片づけをちゃんとできる人になりましょうね」という意味です。
とは言え、節目という本来の意味合いからあまり長々と飾っているのも季節感に欠けるもの。
湿気はシミやカビの原因になるお人形の大敵です。お天気の良い日が続く日を選んで、旧節句が過ぎる頃には片付けることをお勧めします。
◆五月飾りは飾る時期/しまう時期に詳しい決まりごとはありませんが、春のお彼岸過ぎから4月中旬頃までに飾るのが一般的です。
雪国の新潟県内でも春らしい晴れ間が増え、なんとなく気分も上向いてくる時期になるとお家の庭先や畑に鯉のぼりが泳ぎ始めるようです(弊社三条工場の大型鯉のぼりも春彼岸頃から掲揚しております)。
お節句が終わった後、しまう時期に関しては雛人形同様に五月飾りも湿気対策としてお天気の良い日が続いた日を選んで片付けてください。
兜は守り神として一年中出しててもよいという説もありますが、その場合は日々のお手入れに気を遣う必要があります。
鯉のぼりは埃を払い落として色移りを避けるためよく乾かしてからお片付けをお願いします。
A:家の中の湿度のなるべく無い所で、出来るだけ高所箇所をお進めします。
『重いし、場所をとるから…』と押し入れの下段や、納戸に片づけておられる方がいらっしゃいますが湿気の多い環境ではほんの数ヶ月で一気に傷む恐れがあります。
やむ負えない場合は除湿器の設置や容量の大きめの除湿剤をご利用いただいたり、折々の換気などの湿気対策をお願いします。
なお、化学変化によりシミや変色を引き起こす可能性があるため、保存剤は毎年必ず同じものを1種類のみでお使いください。
雛人形には、直接保存剤がふれないよう箱の中にいれて頂きます。お顔には必ず柔らかい紙を当てて、出し入れの際には必ず手袋をして直接手で触れぬようご注意下さい。
五月飾りは、金属を沢山使っているため防虫剤などの使用はお勧めしていません。
そのため、パパ・ママ間の認識すり合わせとご両家での確認がとても重要です。
よくあるのが「買ったのに相手の家からも相談なく送ってきて2個になってしまった」「あちらがいつまで経っても送ってこない」というトラブル…後々まで尾を引くになることもございます。
大切な赤ちゃんの初節句にご家族がなんだかギクシャクしてしまう状況になることは避けましょう。
昔は雛人形は嫁入り道具として嫁ぎ先へ持参したものでした。そのため、今でも母方の実家から贈る事が多いようです。
五月飾りは昔は内飾り(五月人形)と外飾り(こいのぼりと幟旗)の両方を用意することが多かったため、父方で内飾りを買ったら外飾りは母方と分担して贈る事が多かったようです。
なお、地域的な習慣としては、東日本は女の子が生まれた場合は母方・男の子が生まれた場合は家の跡継ぎとして父方が買うことが多く、西日本では生まれた子の性別を問わず嫁ぎ元となる母方実家が購入することが一般的とのことです(※ ご両家が同じ市内でも、かつての藩や村で違う習慣の場合も多々見受けられます)。
可愛い赤ちゃんの為にと両家で折半されたり、お節句の飾りは母方・初節句のお祝いの宴席は父方でなどとお話し合いをされるご家族が増えているように感じます。
しかし、赤ちゃんの一生のお守りとなるため長い目で見たときに定番に近いスタイルが飽きがないので落ち着くかと思います…という説明をお客様には申し上げています。
五月飾りは大河ドラマなどの影響で特定の武将に関するお問合せが多い年も稀にありますが、ご当地の武将かオーソドックスな大将兜が好まれる傾向が強いです。
こいのぼりは住宅事情の変化によって大型商品よりも水袋で重しをするスタンド型や室内鯉へ顕著な主流に変わりました。
すべての方位の災厄を除けてくれますので、飾る際に神経質に方位を気にする必要性はありません。
気にしていただきたいのは飾る環境です。
直射日光と極度の乾燥、高温多湿が大敵なので、そこだけは何卒ご注意ください。
現在は飾る場所として主流なのはリビング、次いであれば和室、少し大きくなったお子さまには本人の子供部屋が多いかと思います。
基本的には「ご家族が集まりやすい場所」に飾るとよいでしょう。
お子さまの健やかな成長への願いを込めたものなので、ご家族の皆様の目に留まりやすい場所に飾ることをおすすめします。
平飾りやケース飾りの場合に「床に直接飾れないし、どうしよう…」とのお悩みも多いですが、リビングであればテレビ台、サイドボードの上に飾る方が多いようです。
和室は床の間があればそのまま飾ることができます。
また、どこのお部屋でも低めのテーブルを出したり、カラーボックスを横向きにしたりして少し高さを出す台を作ってから毛氈などを敷くと目隠しをしつつ空間に区切りがついて華やかにお飾りいただけます。
収納飾りや段飾りはそのまま飾っていただいても大丈夫です。
イヤイヤ期でママやパパたちの指示が難しい時期もあります。
思わぬはずみで付属する小物やお道具でケガをしてしまったら大変です。
背の高めな棚の上など手の届かない安定した場所に飾る、その年だけと割り切ってお人形や兜本体だけで戸棚の中に飾る、ベビーサークルで囲うなどアクシデントを未然に防ぐ工夫をお願いします。
弊社スタッフの姪はイヤイヤ期に積み木をぶん投げてケース飾りを割りました…当たり所が悪いとケース入りであっても破損する可能性はございます。
直接触れられなくて安心ではあるのですがこのような事故にはご注意ください。
=番外編=
飾る場所をなんとなく考えている際に割と候補に挙がるのが玄関とキッチンカウンターです。
玄関は下駄箱や作り付けの棚があって、キッチンカウンターもいずれも大人の腰以上の高さになって安定しており飾るのにいいのでは?と思うのですが落とし穴が潜んでいます。
まず玄関は風除室がある二重玄関やマンションで内廊下などであれば良いのですが、そうでない場合は風雨の日にドアを開け閉めした際の吹き込み・傘の水滴による湿度上昇、埃などもたまりやすい傾向があります。
キッチンカウンターもやはり炊事や洗い物の際の水滴や油撥ね、油分を含んだ埃などの恐れが多々あります。
油分と湿気と埃が絡み合うとカビやシミ発生の危険性が一気に跳ね上がります。
玄関・キッチン近くをご検討の際は不具合を防ぐ意味でもケース飾りや別注ケースを誂えるのがおすすめです。
一生のお守りとして、昔ながらの「3代飾り」に従って存命中の方の物を毎年全て飾っているお宅もあります。
◆雛人形は「女の子が結婚するまでは飾る」と言われることがあります。
これは男雛・女雛が幸せなカップルを表しているように、かつてはお嫁入りが女の子のゴールとされていたからです。
現代では結婚にこだわらず、一人前の女性へ成長すれば雛人形に込められた祈りは満願となり、雛人形は役目を果たしたと考えられます。
◆五月人形は立身出世を祈ると考えたときに「〇歳~〇歳まで」といった明確な区切りはできません。
あえて期限を決めるとすれば…かつては元服を以て一人前の男性として扱われるようになったことから、各種学校の卒業や成人式などを機にするのが良いのではないでしょうか。
「自立した=子どもの身代わりが不要」と、親側が感じた時を目安とするのがおすすめです。
A:人形供養へ出される事をお勧めしています。
何らかの宗教やオカルト的な観点ではなく、お雛様や五月飾りが赤ちゃんの身代わり・厄除けとして贈られるものであり、健やかな成長を願って贈った方がお人形へ託した想いを粗末にしないという心情から、人形供養という形を以てお別れをしていただくのがよいのではないかと思います。
弊社では独自の人形供養を催行していないため、日本人形協会の人形供養サービスや下記の県内寺社などをご案内しております。
また、本当に全く気になされないのであればお住まいの自治体のゴミ分別に沿って廃棄していただくことが可能です。
・新潟縣護国神社
・国上寺
・千蔵院
その他セレモニーホール等で催行されております。
現代はいつも誰かが家にいるというわけではないので、配送の受取日は土日がほとんどです。必ず大安でないとダメというと大変ですね。
ただ、せっかくの赤ちゃんのお祝いの品物ですから縁起を担いだ方が気分的に良いかと思います。
また縁起の良い日は忙しくて飾れないというような場合は、縁起の良い日や時間帯に封を切って箱だけ開け、別の日に飾りつけると良いでしょう。
大安以外にも一日の中に吉とされる時間帯がたくさんありますので、時間帯を選んで飾り付けを始めていただくとよいと思います。 お日柄と時間帯については、以下を参考にしてください。
大安・・一日中、吉
友引・・朝夕は、吉
先勝・・午前中は吉、昼以降は安静が吉
先負・・午前中は安静が吉、午後から吉
赤口・・正午ごろ、吉
仏滅・・一日中、安静が吉
お雛様は元来、上巳の節句に紙で作った人形(ひとがた)の形代で体を撫で、自分の身の穢れを移し川に流した、厄払いの行事に由来しています。
そのためお雛様そのものは、家を守ったり、その家の女性すべてを守るものではなく、女の子一人一人、それぞれのお守りです。
ママのお雛様はママのお守り、姉妹のお姉ちゃんのお雛様はお姉ちゃんのお守りです。
そしてご両親的には全員に同じくらい深い愛情を注いでいるとはいえ、「お姉ちゃんはお雛様あっていいな~私ないのに!」と言われてしまったというご家族様が割といらっしゃいます。
娘一人に一つずつ用意し、お嫁入りする時に持たせてあげるものとされていた背景からも出来れば姉妹間には差をつけずに用意してさしあげたいものですね。
「OK,意味は分かった。でも実際問題お雛様2つ飾るにはスペースや収納場所がない」という方もいらっしゃると思います。
その上で、妹さん用におすすめなのがコンパクトサイズのひな人形や、市松人形、つるし飾りなどです。
各種ご用意ございます。何なりとご相談ください!
武家社会の風習では神社やお寺へ合戦の前に身の安全や家門の盛栄を祈る際に鎧や兜を奉納していました。武将にとって兜や鎧は自分の身を守る防具であり、家のシンボルを表す大切な道具でもあったのです。
その個々人の大切な鎧兜を風に当てて手入れをして飾ったことが由来となり、後に泰平の世へと変わっていくなかで鎧兜の「身体を守るもの」という意味が重視され、病や怪我などから大切な子供を守ってくれるようにという無病息災を願うようになりました。
鎧兜は個人毎の所有物であり、男の子一人一人にそれぞれのお守りとされます。
パパのはパパの、兄弟のお兄ちゃんの鎧兜はお兄ちゃんのお守りです。
やはり幼いご次男やご三男の視点から見ると「お兄ちゃんには五月人形があるけど自分にはない」というのは少し寂しく感じます。
「鎧兜が二つはちょっと…」と思われる場合は小さな収納飾りや可愛い大将人形、鯉のぼりなどはいかがでしょうか?
ご相談いただければ一緒に悩ませていただきます!
お雛様を母方の実家から贈られた際に、父方の実家が先にお雛様をお迎えする市松人形を用意するという習慣のある地方があります。
雛祭りに父方のおじいちゃん、おばあちゃんから贈り物として記念になるということで人気です。
市松人形もお雛様と同様、形代の役目をすると昔から言われています。お雛様と並べて飾って初節句をするとより一層華やかなお祝いになりますね。
羽子板・破魔弓は赤ちゃんが生まれて初めてのお正月を迎える「初正月」のお祝いとして贈る地方があり、邪気を撥ね退けて無事に成長するように願うためのお飾りです。
昔はお正月に歳を重ねる数え年で年齢を数えていたので、赤ちゃんにとっては初めて歳を重ねる日で特別なお正月という位置づけになり、今で言う初めてのお誕生日を盛大にお祝いしていました。
また、医療が未発達で栄養も乏しかった昔は無事に大人になるのが難しかったため、親は子どもが健やかに成長することを願って節目節目を大切に祝ったそうです。
どちらも新潟県内ではあまり根付いていない風習ですが、「飾ると華やかなので欲しい」「嫁ぎ先の方の風習で必要なのですが…」と年に数件はお問合せを頂戴します。カタログから選んでいただく形で弊社でもお取り扱いございます。
厄払いという側面もあり、節句料理に旬の食材を取り入れることで自分の生命力を高める(=邪気を払う)という考え方もいいかもしれません。
白酒・・最近はスーパーなどにもありますが、甘酒で代用してもいいようです。
魚・・・春告げ魚である鰆や鰊、お祝い定番の鯛など
煮染め・・昆布巻きにしん。くわい(芽が出る)
和え物・・菜の花の胡麻和えなど
ご飯もの・・ちらし寿司(桜でんぶや錦糸卵などで彩り鮮やかに)
椀・・・はまぐりの潮汁
お菓子・・雛あられや桜餅、最近は食べられる菱餅もあるようです
京都や関西では雛祭りに笹カレイを御膳に載せるという地域もあります。
伝統食や和の縁起の良い食材を取り入れたおもてなし料理も素敵ですが、定番にとらわれず、何より主役のお子さんに喜んでもらえるお料理でご家庭ごとで楽しいお祝いをお迎えください。
菱餅を模した三色のゼリーやケーキも華やかで写真映えしますよ!
赤ちゃんも離乳食が始まっていたら可愛いレシピがレシピサイトに沢山載っているので思い出作りにいかがでしょうか。
これという定番料理は無いようですが、厄払いという側面もあることから節句料理に旬の食材を取り入れることで自分の生命力を高める(=邪気を払う)という考え方もいいかもしれません。
でも、一から考えるのは大変…というパパとママに縁起を担いだ一例として挙げてみます。
柏餅・粽・・和菓子屋さんに早めに予約を。
魚・・・鯛の尾頭付きや出世魚の鰤や鱸。「人生がうなぎ上りに」と鰻を用意する地方もあるそうです。
煮染め・・若竹煮や土佐煮(筍のようにすくすく成長するように)
和え物・・タコときゅうりの酢の物や白和え
ご飯もの・・赤飯orたけのこの炊き込みご飯
椀・・・海老真薯のお澄まし(腰が曲がるほど長生きするように)
お菓子・・草餅(蓬は薬草。健康や長寿を願ったと言われています)
お赤飯に代えて、手巻き寿司やちらし寿司にしても食卓が華やかになるかと思います。
縁起の良い食材を取り入れた料理も素敵ですが、こどもの日はGW中のお休みでお天気の良い時期なのでご家族そろってBBQというのも賑やかで楽しいお祝いになりそうです。
春巻きの皮で兜を折るレシピなどもSNSで人気ですね!
赤ちゃんも離乳食が始まっていたら可愛いレシピがレシピサイトに沢山載っているので思い出作りにいかがでしょうか。
地方によってはより華やかに、お祝いをいただいたご近所の方もお呼びする場合もあります。
ただ、最近はご両家親族の内々でのお祝いが主流です。
赤ちゃんは多くの人に囲まれて長時間過ごすことに慣れていませんし、大々的なお祝い会を行うことでママ・パパが育児と並行しての準備に追われて疲れてしまわないようにとの配慮からあまり大げさには行わなくなってきています。
なお、ベビーシャワーをお友だちが開いてくれたお返しとして初節句に赤ちゃんのお披露目会をするご家庭もあるようです。いつか新しい伝統になるかもしれませんね!
お祝い返しの品は昔の定番はお赤飯・お菓子・紅白の角砂糖でしたが、最近は可愛い名入れのスイーツやカタログギフトが人気です。
お返しの額はお祝いにいただいた1/3~半額が目安になります。近しいご親族から高額のお祝いをいただいた場合には1/3よりも少ない金額でもかまいません。ご家族で話し合って予算を決めましょう。
水引は紅白の蝶結び、熨斗つきのかけ紙に「内祝い」「初節句内祝」という表書きが一般的。
お祝いをもらった赤ちゃんが贈る物になりますので、水引の下の部分のには名字やご両親の名前ではなく、赤ちゃんの名前を書くようにしてください。
お返しの品物と一緒に赤ちゃんの写真を添えるとなお一層喜ばれるようです。
名前旗のルーツは「のぼり旗」です。戦国時代は合戦の際、敵と味方がすぐに分かるように自分たちの家紋や文字が入った旗を立てて自分達の存在を知らせていました。
飾り物の隣に名前旗を飾ると「その赤ちゃんの物」と印象付けるため、つるし飾りや室内鯉と並んで近年では特に人気が出ています。
命名書の代わりとなる記念品としても節句以外でもお子さまのお祝い事のたびに活用しやすく、お宮参り、お食い初め、七五三、お誕生日のお祝いなどでも飾ることが出来ます。
生地や絵柄、刺繍の糸色などさまざまなものがあり、小さなものでも華やかなデザインから単体で存在感のある物が多いです。サイズ展開も豊富で、組み立て式のため収納時にも場所をとりません。
また、どうしても兄弟姉妹一人一人に五月飾りや雛人形を用意できない場合も、それぞれの名前旗があることでお子様が「自分のために用意されたもの」と思うことができます。
名前旗はごきょうだいにお揃いでも統一感があって素敵ですし、あえて異なるデザインや絵柄を選んでもお子さま自身の特別感を増します。
購入を検討しているママ・パパはぴったりの名前旗を見つけてみてくださいね。
ただし、名前旗などのお名前入れ商品は製作に1~2週間程度かかります。
お節句までに間に合わせたい、お祝い会の日が決まっているなど到着の日付指定がある場合はお早めのご来店をお願いいたします。
<2023年 お名前入れ商品の節句当日までの到着確約〆切>
女の子向け:2月18日頃
男の子向け:4月15日頃(メーカーが4月下旬で季節営業を終了するため〆切が早いです)
親王手持ち小道具類(扇・笏・冠・刀)は現行品サイズで対応できる場合は直ぐにご用意できます。店頭にてご用意がないサイズの場合は製造もしくは取り寄せ可能かお調べいたします。
官女の手持ち小道具、五人囃子の楽器類、随身の弓矢、仕丁の手持ち小道具などもその小道具を持つお人形を必ずご持参いただきますようお願いいたします。
段飾りの牛車など道具類は、お持ちの物とはデザインが変わってもよろしければサイズを合わせてお誂えします。
なお、雪洞や菱餅、桜橘などの対で飾るものは一対での販売となりますことご了承ください。
台や屏風をお求めの場合は親王のお人形を対でお持ちいただき、大きさをご相談した上で製造可能かお調べいたします。
単品のお人形は親王とのバランスや台によりお人形の大きさが決まります。現在は親王飾りが主流のため、官女以下のお人形は受注製作となります。
五月飾りの弓・太刀の添え飾りは一対での販売です。現行品は店頭ですぐご用意いたします。
鯉のぼりの部品や単品鯉は各こいのぼりメーカーからの取り寄せとなるため、1週間ほどでご用意いたします。
・三人官女、五人囃子のお人形
・手持ち小道具類(扇・笏・冠・刀)、(三方・長柄杓・手提げ杓)など ※原則()内セット。サイズによりバラ売り可。
・冠の嬰
・口花(花瓶に挿す花)
・屏風と毛氈
・段飾り台
・こいのぼりをロープと繋ぐ金具 ※メーカーごとに仕様が違うためお手持ちの物を1つお持ちください。
・矢車(鯉のぼりのポールの上で回る風車状のもの)
・着用兜の前立
・名前旗の房 ※左右一対での販売
そのままで修繕が可能なのか、部品交換となるか、修理が不可能かはお写真や現物を見てみない事には申し訳ありませんがお伝え出来ません。
例えば、「毎年出し入れしてたら何となく髪の表面がほつれてきた」や「兜の縅に白カビが発生してしまった」「桜橘が歪んでしまった」というようなお申し出であればしばらくお預かりして整髪やカビの除去、枝ぶりの整容などさせていただきます。
また、「手が折れてしまった」「女雛の裳にシミが出た」「鍬形が曲がった」等の部品交換可能な部位であれば大きさに合わせて交換をします。
お人形は頭や手、衣装では女雛の裳・男雛の裾であれば交換にて修理が可能です。
なお、頭は職人が一つずつ手作りしているため、継続品で同じ商品番号の物と交換となっても顔立ちや微妙な肌の色味が変わります。
お持ちのお人形の頭が廃盤となっている場合は現行品の中からお選びいただくことになります。
シミやカビなどの不具合が胴体や袖部分だと修繕や交換は基本的にお受けできません。
お雛様の着せ替えのお問い合わせも時折頂戴致しますが、一から作るより手がかかり、後々形が崩れるなど別の大きな不具合が生じる可能性もあって大抵のお人形は新調したほうが安価となります。
どうしても…という場合は、弊社の製造したものに限り、ご相談とさせていただきます。その場合ご購入価格より高額となる可能性を予めご了承ください。
段飾りをやめて親王飾りにしたり、鎧の兜だけを飾れるようにしたりすることも可能ですし、それを飾る台やお屏風・小道具類を改めることで雰囲気を変えて大人らしい季節の飾りとしてお楽しみいただけるようにすることもできます。
昔ながらの黒枠の金屏風を本総風で色箔のものや金彩の入った屏風に変えたり、平台、雪洞や桜橘など小道具を現代風のもので誂えたりすることも可能です。
また、台を使わずカラー毛氈で飾るなど色々ご提案させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
台・屏風の試作などを行う場合は2か月~半年ほどお時間かかることがございます。何卒ご了承ください。
お祝いの他にもお守りや厄除けの意味もあり、着物や節句飾りだけでなく日常品の中にも多数あしらわれています。
代表的な吉祥文様や絵柄の意味をご紹介します。
◆亀甲
正倉院宝物にも見られるほど歴史のある文様で、亀の甲羅に由来する六角形をしています。亀は万年と言われるように「長寿」の象徴。これを複数連ねることで「永遠の繁栄」を願う文様になります。
◆七宝
円を斜め四方に重ねて輪をつないでいった吉祥文様で、仏教における金・銀・水晶・瑠璃・瑪瑙・珊瑚・シャコ貝の七つの宝を指し、裕福さや高貴さの象徴。
輪は「和」に繋がり、それがどこまでも永遠に続くことから「円満」や「繁栄」といった意味が込められています。
◆市松
二色の正方形が交互に並んだ格子柄で、その柄が途切れることなく続いて行くことから「無限の繁栄」の意味が込められています。
◆麻の葉
実際の麻の葉っぱに似た正六角形を描く幾何学模様。麻の葉は成長が早くまっすぐに伸びていくため「魔除け」や「子どもの健やかな成長」の願いが込められています。
◆青海波
古代ペルシャが発祥とされる吉祥文様で、扇状に重なった同心円が、大海原に無限に広がる波を表しています。「平穏で幸せな暮らしが未来永劫続く」ことを願っています。
また、波は何度も押し寄せ岩の形や地形をも変えてしまうことから、強い意志を持ち、あきらめず何度でもチャレンジする不撓不屈の精神を願う柄でもあります。
◆流水
絶えず止まることなく流れる水は清らかで美しく、常に新しく変わりながら姿をとどめている水の流れから、変わり続けていく未来を表しています。「厄除け」や「火から身を守る」という願いも込められています。
◆雲取り
空に雲がたなびく様子を輪郭線や鮮やかな色柄で表現しています。神秘的に色や形を変え、龍や神様が住んでいるとされていた雲は「瑞祥」や「運気上昇のしるし」として尊ばれています。
◆鞠
女の子が生まれると魔除けとして鞠を贈る習慣があります。高貴で雅やかな雰囲気と色鮮やかで華のあるデザインは勿論のこと、その形状から「どんな困難も丸く収まる」「弾むような幸せがいつまでも続く」ようにと願いが込められた鞠の絵柄は広く愛されています。
また、玩具は子供にとって欠かせないものでどこに行っても寂しくないようにするお守りという説もあるようです。
◆組紐
組紐は、奈良時代から伝わる細い絹糸を幾通りにも組み合わせた工芸品。繊細で優美なモチーフで「結ぶ」ことが魔除けを意味するとされています。
◆熨斗
のしは元は鮑の肉を薄く引き伸ばして乾燥させた“のしあわび”のことで、「長寿」を象徴するものとして神社のお供え物や贈答品に使われています。
これを和紙に包んだ贈り物をモチーフにした細長い帯状のものが吉祥文様として図案化されました。この柄をいくつも束ねた熨斗目は、多くの人から祝福を受けていることと、その幸せを周囲にも分け合うという意味があります。人との絆、繋がりを表すとてもおめでたい文様です。
◆雪輪
特徴的でかわいい形は雪の結晶を表したもの。雪が解けると水になり、農作物を豊かに育む源になることから「豊穣」の願いが込められています。
◆貝桶
貝合わせは平安時代から伝わる貴族の遊びで、美しい絵を描いた左右一対の貝殻から対となる貝殻をさがすもの。他の貝とはぴったり合わない二枚一組の貝は「永遠の契り」や「夫婦円満」を意味し、貝桶もおめでたいものとされています。
このような背景から「夫婦円満」「貞節」の願いを込めて現代まで愛されつづけている吉祥文様です。
◆御所車
平安時代の御所車は貴族など限られた人しか使えなかったことから「富」と「華やかさ」の象徴とされてきました。この御所車に四季の花をあしらった花車という柄は「たくさんの幸せを招きますように」という意味も込められています。
◆扇
扇は広げると要から末が広がっていく形状から末広とも呼ばれ、運気が良くなる・将来の展望が明るいということを表し「発展」や「栄光」を象徴する吉祥文様です。
また、扇で仰ぐ所作は神霊を呼び起こして物の霊を揺り動かす力を備えると言われ、神楽や能楽・田楽などの芸能にも欠かせないものとされます。扇面や扇子文、檜扇文など多数の文様が派生しました。
◆糸巻き
蚕糸や染めた糸を巻きつける道具の糸巻がモチーフ。糸巻は千切とも呼ばれることから、「人との仲を固く結ぶ」という意味を持ちます。長く伸びる糸は「長寿」を表す縁起物でもあります。
◆宝尽くし
打出の小槌や隠れ蓑、金嚢、如意宝珠、分銅などの宝物を集めた文様です。これらすべての要素がそろわなくても宝尽くしと呼ばれます。その名の通り「富裕」「福徳」の象徴で、魔を祓い福を招く文様です。
◆薬玉
毬に蝶結びの房が下がったような柄が描かれている模様です。端午の節句ではくす玉に蓮や菖蒲などを詰めて花と糸で飾り、魔よけの5色の糸を下げます。
「無病息災」の願いが込められた文様です。
◆四君子
梅・菊・蘭・竹の4種の植物が揃った吉祥文様です。
君子とは古代中国で徳が高い人格者で清らかで高潔な優れた人のことを指し、それぞれが君子を思わせる佇まいと風格を持つことから四君子という柄として好まれるようになりました。
◆松竹梅
「三寒三友」と言われ古来中国より尊ばれてきました。逆境にあっても節操を守る例えとされており、日本でも古くから祝儀に欠かせないもの。
松は”神が宿る木”とも呼ばれ常緑樹であることから「不老長寿」、竹は成長が早くまっすぐに伸びて丈夫なことから「成長祈願」、梅には冬を耐え春一番に花を咲かせることから「生命力」「子孫繁栄」の意味も。
◆桜
古い言葉で桜の”サ”は田の神・穀霊、”クラ”は神座(神のいる場所)を意味し、「五穀豊穣」の象徴。春にはたくさんの花が芽吹くため、春の花の象徴でもある桜は「縁起の良い物事の始まり」を意味するとされています。
◆藤
平安時代に活躍した藤原氏の繁栄とともに高貴な花とされ、“不死”と同じ響きから「長寿」や「子孫繁栄」を表します。下向きにしだれるように咲く花穂が天と地をつなぐものとして敬われました。
◆菖蒲
古くから解毒作用がある薬草として人々から重宝されていました。そして菖蒲の葉のもつ香りは厄災を払うとされ、魔除けのお守りであると信じられていました。
また、菖蒲の読みは尚武や勝負と同じ音であることから武家に愛され、立身出世の願いも込められています。
◆桐
「鳳凰が出現すると天子の治世となる(平和な世の中になる)」という伝説から鳳凰が住む桐の木は高貴なものとされており、「人格の高さ」「徳」を表す人気の吉祥文です。「鳳凰は桐の木に棲み、竹の実を食べる」という言い伝えから桐竹鳳凰という吉祥文様は皇室専用の文様にもなるほど。
◆牡丹
古くから百花の王や豊年の兆しとなるめでたい花の瑞花として「幸福」「富貴」の象徴に描かれます。また、牡丹の“丹”は不老不死の仙薬を意味することから「不老長寿」という願いも込められています。
また、百獣の王と百花の王の組み合わせである唐獅子牡丹は、獅子の命を奪う身中の虫は牡丹の夜露にあたると死んでしまうため獅子にとって牡丹の側が安らぎの場所であるとして、最上の組み合わせを意味する大変縁起がいい柄とされています。
◆橘
『古事記』でも不老不死の理想郷に生え、「長寿」や「子孫繁栄」をもたらす縁起の良い常緑低木。ハート型の果実と花葉がかわいく描かれた文様です。
◆葡萄・蔦
3000年以上前から使われており、葡萄はたくさんの実をつけることから「豊穣」、広く伸びていく蔦や唐草は「子孫繁栄」を表します。
◆菊
菊は古くから薬として使われ、九月九日の重陽の節句には菊についた露を飲むと不老長寿になるとの言い伝えから長命を祈る風習があります。また、その美しさから気高さや上品さも表しており、「邪気を祓う」「長命」「無病息災」の象徴とされていました。
◆鶴
鶴は千年という言葉があるように、「長寿」や「生命力の豊かさ」を象徴しています。しなやかな姿は美しさや高貴さを際立たせ、慶事にも多く使われています。
また、鶴の特性でつがいが仲良く一生を添い遂げることから「夫婦円満」の象徴でもあります。
◆蝶
その美しさやひらひらと優美に舞う愛らしさが目を引きますが、その成長過程から「立身出世」や「不死不滅」といった意味が込められており、性別関係なくお使いいただけます。
◆うさぎ
うさぎは月の使いとも言われ「ツキを呼ぶ」縁起の良い動物とされています。その動きから「跳躍・飛躍」を表し、子沢山であることから「豊穣」「子孫繁栄」の象徴であり、長い耳は福を集めると言われています。
古くから春の象徴とされ、優しく穏やかな姿は家内安泰と平和をも意味し「物事がとんとん拍子に進む」ようにと願う縁起の良い柄です。
◆鷹
鷹は大空高く舞い上がり、地上の小動物を見つけ獲物とします。はるか先まで見渡せるその眼を千里眼になぞらえて「先を見通す眼力」、「もの事の本質を見抜く眼力」を持って欲しいという願いを、また獲物をがっちり掴むその爪は、運や幸運をしっかり掴んで離さないという意味を表しているそうです。
◆龍
龍は元々大地と水の神とされ、天に昇るその姿から「出世」や「飛躍」の意味が込められています。また、伝説や神話から広く親しまれ、中国皇帝のシンボルに使われたことから「高貴さ」や「力強さ」を表し、あらゆる邪を征して一族の安泰と繁栄とをもたらす神的な力の象徴として選ばれることも多い柄です。
◆鯉
鯉は生命力の高い魚で濁り水でも清水でも生きることができることから「厳しい環境であっても生き抜くように」との願いが込められています。また鯉が滝を登りきると龍になる登龍門という故事から「立身出世」の象徴でもあります。
◆虎
古くから虎は王者の象徴で縁起のよい生き物と考えられ、その吠える姿は虎嘯と呼ばれ「立身出世」「大成」を意味します。虎のように強く、たくましい子に育って欲しいと願いが込められています。
また虎は一日で千里行って千里還ると言われることから人生の見通しがきくとされ、「勇敢で先を見通せる」ようにと人気があります。
現在の暦の3月3日は、旧暦では2月3日にあたります。古来の風習を守って、旧暦の3月3日(現在の暦では4月3日頃)にお祝いする地方も多々あり、「月遅れの雛祭り」といいます。
有名なのは、庄内地方の雛祭り。また京都や歴史ある家柄の末裔のお家では、古くからの慣習を守り、旧暦で雛祭りを行うことも多いようです。かの冷泉院の末裔 冷泉家も旧暦で雛祭りを行っているそうです。
3月はまだ冷えますし、ママ・赤ちゃんの体調や色々な都合で3月3日に初節句のお祝いが難しい場合は無理をせずともよいと思います。
古式に習って旧節句でお祝いするのも素敵ですよ。
大切なお雛様もゆっくり飾っておくこともできて楽しみが長く続きます。
木彫頭・・歴史的には最も古く、木から頭の形やお顔の凹凸を彫り出して胡粉で白塗や彩色を施すもの。「正頭」とも呼ばれ、製作が困難なため現在はほぼ使われていません。一刀彫の人形とはまた別物です。
桐塑頭・・江戸中期の岩槻藩の発祥で現在は作り手も少なく非常に貴重。桐粉と正麩と混ぜて練ったものを型で成形し、置上げといって胡粉と膠を硬く練り、目・鼻・口を熟練職人の感覚で盛り上げるため同じお顔が一つとしてないと言われます。
ただ、自然素材のため作業時期や環境などに影響を受けやすく、桐粉と胡粉の相性の関係上ひび割れ等が発生する事もあり、表情の安定性の件も相まって現在の石膏頭に主流が移行。「本練頭」とも呼ばれます。
石膏頭・・現代の主流。石膏を型をつかって成形し、胡粉で仕上げるタイプの頭。石膏製といっても型作りから抜き、目切りやお化粧の彩色に至るまで伝統的な手作業で頭師が作りあげるため一つ一つお顔立ちに微妙な差異があります。
昨今は女性や若手の職人の参入もあり、日本人形の顔立ちが怖いという声を受けてお目目パッチリな可愛らしいお顔や現代的なメイクが映える美人顔なども生まれています。
さて、「本頭」についてですが…諸説ありますが、かつて大量生産のために海外で粗製濫造された石膏頭や最近では3Dプリンター製の頭があるため、そのようなものとの差別化に頭師が作った石膏頭を「本頭」と呼んでいることが他店様ではあるようです。
弊社ではごく一部の桐塑頭の他、石膏頭は頭師が国内にて製造したもののみを取り扱っているため「本頭」と呼称しておりませんが物としては同じです。
人形店にはそれぞれで独特の呼称・特長の名付けをしているものがございます。御不明点等ありましたら何なりとご相談ください(わからないことも出来る限りお調べします!)。
日本人形が見慣れず怖い…というお客様のお声から生まれた可愛らしくパッチリした目の現代風のお顔も人気です。

衣装着のお雛様
普段良く目にするのは、実際の着物を着ているように見えるように作られた衣装着のお雛様に使われているお顔ですが、これは主流が二種類あります。
一つは「関東風」と言われる細面にはっきりとした目鼻立ちの現代的なお顔。もう一つは、目が切れ長で細くお公家さん風の上品な顔立ちの「京顔」と言われるものです。

木目込みのお雛様
杢やウレタンの型に筋目を入れて衣装を着せ付けることから「木目込(きめこみ)」とよばれるお雛様は、ふっくらとして味のあるまるっこい顔に目を細い筆で何度も重ねて描く「笹目」または「描き目」で仕上げられていてほんわか可愛らしいお顔立ちが特徴です。

おぼこのお雛様
「おぼこ顔」と言って、ふくふくとした丸い顔立ちの幼子のような可愛らしいお雛様もあります。衣装着、木目込みともに小さなサイズに比較的よく見られます。

お雛様は関東と関西では、お殿様とお姫様の位置が違います。
関西では古来よりの朝廷の儀式に習い、紫宸殿を背にして左が上位とする飾り方をしているので雛壇を背にして左側(向かって右)にお殿様を飾ります。
これに対し関東では、昭和天皇御即位の礼の流派に習い、右に男性が立つスタイルを取り入れ、以来、雛壇を背にして右側(向かって左)にお殿様を飾るようになったとする説があります。
別の説によると、東日本でお雛様が上位である左に置かれるのは、徳川家康の孫である興子内親王が後に即位し明星天皇となってから、古事に習い江戸では上位の左に女雛を置くようになったという説もあります。
というわけで、京風のお雛様の場合は、宮廷式にならって、お殿様を向かって右に飾ると良いでしょう。
それ以外の場合は、それぞれのおうちのご出身や家風にあわせてお飾りいただいてよろしいと思います。
雛祭りは平安時代に古代中国から輸入された習慣である季節の節目に災厄を祓う『五節句』のひとつ、上巳の節句に由来しています。
古来より桃は邪気を祓って薬効が高いとされており、上巳の節句が3月上旬という桃が咲く季節でもあるため「桃の節句」と呼ばれるようになりました。
一方、桜と橘も「魔除け」「邪気払い」「不老長寿」の力があるとされる縁起の良い植物です。
京都御所紫宸殿南庭に対で植えられており、宮中警固などを行う左近衛・右近衛がこの近くに配陣されていたことから「左近の桜・右近の橘」と呼ばれています。宮中の風習を模したお雛様にも魔よけとして飾られるようになりました。
飾る際には「左近の桜が右、右近の橘が左…?」となりますが、紫宸殿の中からの視点(お雛様目線)で右と左と覚えてください。
眉無しでいいのです!
最近は三人とも眉があるお人形になっているものが増えていますが、本来のお雛様は中央の官女には眉がありません。
これは両側の立ち官女が若い女性なのに対して、中央の眉のない座り官女は少し年配でお目付け役や指導担当のような立場の人。
古来宮中では年配の女性は眉がないのが上品とされていたため、眉が描かれていないのです。
昔のものでは、既婚者として「お歯黒(歯を黒く塗ってある)」をしたお人形や、京風のお雛様では真ん中の官女だけ振袖ではなく短い袖のものもありました。
平安時代のひいな遊びが原型となり、宮廷の女人達が衣装の端切れなどで雛を手作りし始めた頃から作られていたもので、もっとも古い歴史のある人形です。 いわばお雛様のルーツと言っても良い品。古いお雛様で有名な庄内地方でも立雛はたくさん残っています。
立雛は現在は主に木目込や陶器で作られている場合が多いのですが、元々は江戸初期から盛んに雛祭りに飾られた雛人形です。
衣装着の立雛は同じサイズの座り雛よりも大きく装束や襲目などの美しさがよくわかるため、シンプルでありながら華やかです。
通好みの方や先に座り雛がある際の2つ目のお雛様としても人気ですよ。
御殿飾りとは、京都御所などの宮中の建物を模して作られた飾りのことで、実際に高貴な人々が暮らしていた様を表しています。 名古屋の徳川美術館などにも素晴らしい御殿飾りが残されています。
昭和中期には裕福な一般家庭でも時折飾られていました。
現在では作られる数も極めて少なく、いくつかの種類はありますが出来の良い品は少なくなっていますのでぜひ大切にしてください。
メーカーや専門店スタッフでも若い世代だと写真以外で見たことがないという者もおりますので拝見させていただきたいくらいです…!
また、室外に飾る五月飾りを外飾りと言って鯉のぼりや武者絵幟があります。内飾りと外飾りはそれぞれに違った意味があり、どれか一つだけ飾ればよいというものではないと言われます。
【内飾り】
◆鎧・兜
合戦があったころに武将にとって鎧や兜は自分の身を守る欠かせない道具でした。
なので、鎧や兜には「命を守る」という意味合いがあり、「男の子が災害や病気、事故から守ってもらえるように」という願いが込められています。
◆弓太刀
弓矢と太刀は「魔除け」の意味があります。
太刀は刀とは違って戦うための道具ではなく儀式として使われていました。
長い弓は破魔弓で「神様が降りて宿るもの」、太刀は「人を傷つけない儀式と護身のためのもの」として飾られています。
◆武者人形
人形は形代であり、厄や穢れの身代わりになってくれるもの。
伝説上の人物をモデルに様々な武者人形や可愛らしい子供大将人形が制作されており、お子様の健やかな成長を願う身代わりとしての意味があります。
【外飾り】
武者絵幟は御家安泰・子孫繁栄の願い、鯉のぼりは立身出世の願いがこめられています。
◆武者絵幟
勇壮な絵柄と家紋やお子さまの名前が描かれたのぼり旗のことです。
鯉のぼりよりも歴史は古く、かつては浮世絵師なども腕を振るって江戸時代には節句の外飾りの代表格でした。
戦国時代に戦で敵と味方を識別するために自軍の陣に家紋などが入った幟を立ていたものが儀礼化し、江戸時代の泰平の世へと変わると絵幟を立てて近隣へ後継ぎとなる男の子の誕生を知らせて天の神様に『わが家の男の子をお守りください』と加護を願う目印とする意味合いになったと言われています。
◆鯉のぼり
江戸中期に町人によって生み出されました。前記の絵幟には「登竜門図」という定番図柄があり、鯉は滝を登って龍になるという中国の故事にあやかって立身出世を願うものです。
その図から鯉だけを立体におこし、絵幟の付属品としたのが鯉のぼりの始まりです。
最初は真鯉のみのシンプルなものでしたが、時代が下って大正頃から複数匹が仲良く泳ぐ姿となりました。
昨今は全国的に住宅事情から大きな鯉のぼりを外に飾るのが難しくなっているため、内飾りを豪華にして鯉のぼりは室内鯉にしたりスタンド型にする傾向があります。
中部地方の一部や四国・九州の一部では鯉のぼりと武者絵幟はマスト!と豪華な外飾りが習慣的に根強い人気のようです。絵幟はご親族や知人から贈られるものとのことで1本とは限らず、大きなものがズラリと並ぶと壮観です。
なぜなら鎧は全身を守ってくれるものであり、「具足」とも呼びます。具足には不足なく十分に備わっているという意味があるので縁起がなお良いとされるようです。
しかし、兜も一番大事な頭部を守るもの。勿論のことですが初節句の祝いの役目をしっかりと果たします。
小型の鎧、大型の着用兜などもございますのでお好みに合わせてお選びください。
お人形は鎧兜を身に纏っていても可愛らしいので人気です。
有名な武将のデザインや個性的なデザインまでさまざまで節句を華やかに彩ってくれます。ふっくらとした童顔の健やかな表情が親しみやすく、鎧や兜が怖くて苦手という方にもお勧めです。
なお、長男に兜を贈っていた場合は続く兄弟にも格をそろえて良いものか?とお客様からご質問を受けることがあります。
かつて日本には長男が家督を継ぐ習慣の家が多くありました。長男は惣領として家を守り、それを弟たちが支えることも多かったことでしょう。
「格」という見方では鎧と兜は「鎧飾り」>「兜飾り」とされるため、今でも「長男が最も格上」としてご長男には鎧でご次男以下には兜、もしくはご長男に兜の場合はご次男以下にも兜とすすめる向きがあります。
現代には家督制度もありませんので、あまり気にされずお子様に似合うものをお選びください。
「お兄ちゃん着用兜だったけど弟には鎧にするわ」というご家族様もおられますよ!
縁起も気になるところではありますが、人柄を表すエピソードや兜のデザインに込められた意図を重視するなど視点を変えるのはいかがでしょうか?
新潟県ご当地武将と共にいくつか有名武将をご紹介します。
◆上杉謙信◆
【人柄・イメージ】
新潟県ゆかりの武将で「軍神」「越後の龍」と呼ばれ、私利私欲よりも義を重んじる人柄が伝えられています。
有名なものでは内陸の甲斐を領国とする宿敵 武田信玄に対して周辺大名が塩の禁輸をした際、謙信はこれに与せず甲斐領民の苦難を救うべく日本海側から塩を送ったという伝説で「敵に塩を送る」ということわざの語源となったエピソード。別説の「便乗値上げを禁じて正価での流通を維持させた」であっても、敵の窮地につけこむようなことはしない真っ直ぐな心根の方であったことが伺えます。
【兜のデザイン】
出家後の法体頭巾姿のイメージが強いですが、五月人形では日月前立ての兜が主流。
信心深かった謙信は自身を毘沙門天の化身と称していたのが有名ですが、妙見信仰の影響も受けておりその中でも特に月と太陽を信仰していたため日輪と三日月を使ったといわれています。妙見信仰とは北極星を神格化した妙見菩薩に対する信仰のことで、星・月・太陽それぞれ信仰する対象によって派が異なりました。
また、上杉神社所蔵の戦勝神である飯縄権現前立の兜をモデルにした兜も人気です。
◆直江兼続◆
【人柄・イメージ】
新潟県のもう一人のご当地武将、直江兼続は主君 上杉景勝と民のために生きた上杉家重臣です。秀吉の死後、家康は上杉家に謀反の噂があると厳しく問質して服従を求めました。その際に兼続が送った超長文の反論お手紙が有名な「直江状」です。
主家への忠義を尽くす人柄と知性や教養がある情深いイメージです。
【兜のデザイン】
大河ドラマで一躍有名となった「愛」という漢字をモチーフにした前立てが特徴。
この「愛」は、上杉謙信が戦勝祈願をした愛宕神社が由来しているという説と兼続が信仰していた愛染明王から取ったという説があります。
◆織田信長◆
【人柄・イメージ】
三英傑の一人目。比叡山焼き討ちなど強烈なエピソードもありますが、天下布武を目指したリーダーシップがあって決断力もある潔い人柄で人気です。
先進的な考えや物をどんどん取り入れ、新時代を切り開くように挑んでいく姿は現代でも通じる格好良さ。また、お城で祭りを開催したり気前の良いエピソードも多々残っており、庶民からも好かれていたそうでまさに戦国のカリスマです。
【兜のデザイン】
時代劇などの影響でマントに南蛮胴をイメージする人が多いことから、よく見るデザインでは桃型兜を基にして家紋である木瓜紋と御簾の前立てが特徴に。
木瓜紋は中国・唐の時代に窠文を元として鳥の巣を図案化したもので、巣から小鳥が飛び立つことの子孫繁栄の願いが込められています。また御簾は宮殿や寺院の簾であり神の加護を祈る意味があります。
建勲神社が収蔵している兜にも木瓜紋の前立てがあしらわれています。
◆豊臣秀吉◆
【人柄・イメージ】
三英傑の二人目。農民の生まれから信長に仕えて身をおこし、野戦は苦手でも持ち前の明るさと知恵を駆使してどんどん立身出世し天下人にまで登り詰めた日本史上サクセスストーリーの代名詞のような人。
数多のエピソードからも愛嬌がある人たらしで、世渡り上手な人柄が伝わっています。
【兜のデザイン】
有名な「一谷馬蘭後立付兜」は、後頭部に後光が差しているような後立が備え付けられている1刎。この兜は従来の様式に囚われない秀吉の自由奔放さと派手好きな自己顕示欲が大いに表現された天下人の象徴です。
兜鉢は源平合戦の地 一の谷の崖に見立てた形状で、後頭部には馬蘭の葉をモチーフとした29本の後立が特徴。馬蘭は菖蒲の一種で、「勝負」「尚武」と同じ読み方をすることから武将達に好まれました。
◆徳川家康◆
【人柄・イメージ】
三英傑の三人目。長い苦労の時代を過ごした家康は何があっても粘り強く突き進んで最終的に天下を取り、徳川300年の泰平の礎を作ったことから「神君」とも呼ばれます。今も家系が続くことから子孫繁栄のイメージもあります。
秀吉から高価な茶碗を自慢されたときに、家康は「自分は披露できるようなものを持っていないが私のために飛んできてくれる家臣が宝だ」と話したエピソードからも穏やかで人を大切にした人柄がうかがえます。
【兜のデザイン】
大河ドラマなどで若き日に身に着けていた「金陀美具足」が有名ですね。また江戸幕府を開く切欠となった関が原の戦いに持ち込んだと言われる「歯朶具足」は大黒頭巾形兜に繁栄と長寿の対象であるシダの葉をあしらったもので、こちらをイメージした兜も縁起が良いと人気です。
他にも「熊毛植黒糸威具足」や「南蛮胴具足」など様々伝えられています。
◆武田信玄◆
【人柄・イメージ】
「甲斐の虎」と呼ばれた信玄は情報収集力に優れ、さらにはその情報を分析する力にも長けていた戦略家。家臣や領民を大切にしており、周囲の人から信頼が厚かったとされています。
病で亡くなったとされる武田信玄は自分が死んだとなれば敵の士気も高まり、まだ若い息子の指揮では厳しい戦いになると考え「自分が死んだことを隠せ」と言ったといわれています。戦上手で死の間際まで後々の事を冷静に見通していたのです。
【兜のデザイン】
錦絵姿や大河ドラマから真っ赤な鎧と白い毛の付いた兜で軍配を持つ姿のイメージが強い信玄。前立てに金の角をもつ獅噛をあしらい、兜の鉢にはフサフサの白毛が施されている有名な「諏訪法性兜」が人気です。
◆伊達正宗◆
【人柄・イメージ】
奥州の覇者「独眼竜」の名と苛烈なエピソードも伝わる豪快さ、その一方で聡明かつ律儀な性格を持ち合わせ、「伊達男」という言葉からも機知に富んだ格好良さでスマートなイメージ。政宗は自ら台所に立ち、客人に手料理を振舞っていたと言われます。料理に関して「馳走とは旬の品をさりげなく出し、主人自ら調理してもてなす事である。」という意識が高い名言も残しています。
【兜のデザイン】
大きな三日月をモチーフにしたの前立が特徴。政宗も妙見信仰の影響を受けており、月の中でも三日月を選んだのはシルエットの好みと戦時に刀の邪魔にならないためだと言われています。
そんなこだわりもまさに伊達男です。
◆真田幸村◆
本名の真田信繁よりも幸村という名が有名な「日本一の兵」。義理を通して主家に殉じ、大坂の役での勇敢な活躍と悲劇的な状況から決して逃げることなく自らの運命を最後まで全うした華々しい最期が英雄として庶民の間に浸透し、今なお高い人気を誇っています。柔和で辛抱強く、普段は物静かで怒ることはめったになかったと伝えられています。
【兜のデザイン】
鹿の角の鍬形と六文銭の前立が特徴的です。鹿は険しい山道も颯爽と駆け抜ける姿が神秘的な力を持つように見え、古くから神使として大切にされていました。また、六文銭は死後の平安を祈って「三途の川の渡し賃」として棺に六銭投げ込む慣習から生まれたもの。
鹿の角で神の加護を願いつつ、六文銭で戦と死に対する覚悟を表したのでしょう。
パパママ世代においては結婚時に選択した側の名字のルーツから家紋を継ぐことになります。探し方で代表的なものを挙げます。
1.両親や親戚に聞く
聞ければ一番早いですね!!
もしご両親で分からなくても、名字を引き継いでいる家系を遡って祖父母やその兄弟など年配の方に聞けばほぼ確実です。
2.実家や祖父母宅を捜索
仏壇上部や開いたところの下側中央に家紋が入っていることがあります。礼服の羽織袴、お盆の時に見かけるお迎え提灯、冠婚葬祭で使った大きな風呂敷などに家紋が入ってることも多いです。ただ、女性の着物は嫁入り道具として持ち込まれた場合には嫁ぎ元である実家の紋が入っている可能性が高いため注意が必要です。
もしお蔵があれば出入口や屋根の鬼瓦にあしらいがあるかもしれません。
3.引き継いでいる名字側のお墓を調べる
墓石やその周辺に家紋を刻印することはとても一般的。特に寺院の墓所にあるお墓なら大半にあるかと思います。墓石本体に見当たらない場合はろうそく立てや香炉、花立を見てみてください。
家紋が確認できた場合は必ず写真も撮っておきましょう。家紋は微妙な違いがあるので画像で残しておくのが一番確実な方法です。画像検索などで名前も調べておきます。よほど珍しいものでない限り「丸に片喰」「違い鷹の羽」等の紋様を表す名前がついているので、知っておくと誰かに伝えるときに役立ちます。
なお、手を尽くしたけれどどうしても家紋がわからなければご自身の代から家紋を定めてしまうという方法もあります。
かわいいお嬢様のために、ポールの長さに余裕がある場合は単品こいのぼりを追加はいかがでしょうか。
各メーカーが種類ごとカラーバリエーション豊富に製造しておりますので、お持ちのこいのぼりが分かれば最適なサイズでご案内させていただきます。
よくある単品鯉の色味は緑・オレンジ・紫などですが、最近はピンクのこいのぼりもご用意がある商品が増えてまいりました。ぜひお嬢様のお好きな色でお選びください。
男の子のご兄弟が増えた場合も青の鯉を増やすのもいいですが、他の色を選んでいただいても賑やかになりますよ。
もっと手軽に飾るなら物干し台などの2本の柱の間にロープを渡して横向きに飾っていただくこともできます。
ポールもスタンドも矢車も不要になり、必要なのはロープと鯉だけです。
弊社スタッフ自宅では雨樋とベランダ柵の間にロープを張ってこいのぼりを飾っています。斜めだと風が入りやすいのか、軽い風でもなびいて爽やかですよ。
結構な雨でもベランダなら口金具をスライドして建物側に鯉を寄せてしまえばそのまま出しておけますのでご参考までに…
皆さまいろいろなお店を回ったり、何度も足を運んでいただいたりしてお選びになられます。
そのお手伝いをさせていただくのが我々人形店のスタッフですが、一番大切にしていただきたいのは贈るお客様自身で見初めたお人形や五月飾りであることだと思っています。
素材や細部のこだわり、作家である人形師はもちろん品質の保証につながる物で比較する際の重要なファクターとなりえます。
また、スタッフによる専門知識に基づく説明を受けることで、知らなかった歴史的背景や素材や製法の良さを知ったり、文様や絵柄にとても良い云われや縁起が隠されていたり、最初は怖かった頭に得も言われぬ味わいを感じるという価値観や好みの変化も多々あることです。
でも、『良いもの』とは何でしょう?
赤ちゃんの健やかな成長を祈り、厄をよけてくれるように身代わりとするお守りであり、「家族皆があなたの誕生を心待ちにしていたよ。これからも元気に育つことを願っているよ」という大切な思いを言葉だけではなく形に表したものであることが節句人形の存在意義です。
サイズや価格、飾る手間などに目がいきがちかもしれませんが【大切な赤ちゃんのお守りであり、ご家族の心の具現化であり、笑顔と幸せの中で末永くお飾りいただけるもの】という点も是非お選びいただく際のポイントに置いていただければ幸いです。
まずはお店をぐるっと回って心惹かれる節句人形をさがして、その後から気になる点の説明やセット組み換えなどで専門スタッフをご活用いただくのがよろしいかと思います。
当店でもご入店時にまずお声がけをいたしますがゆっくりご覧になりたいなど接客がご不要な際はお気軽にお申し付けください。
必要な際には喜んでお手伝いやご説明させていただきます。
お手頃な商品であっても品質基準を最低限度満たすよう厳選していますが、価格設定において指標となるのは大きく5つの要素です。
1.素材や製法
2.製作者の技術
3.美術的・工芸的な観点
4.希少性や歴史的な価値
5.消費者の求めるもの
1~4を単純化すると《高》伝統的な自然由来の素材や高級材を使用し国内で伝統工芸士など熟練職人が各々の技術の粋を尽くして手作業で作るもの、《低》外国での加工など安価な素材を使い工業製品化され大量製造するものが使用されているかという感じでしょうか。
例えば、【総理大臣賞などを受賞した著名作家が小石丸(蚕の日本在来種の一つで皇后御親蚕に用いられる品種。非常に細く上質の糸を産するが繭糸量が少ないため経済性にかけ「幻の絹」と呼ばれる)の正絹に京友禅・手刺繍を施した生地を使って独自の手法で着付た人形に本金箔の本総屏風や伝統工芸の塗台、道具を添えた一点物の桐塑頭雛人形】などはどこであっても高価格になると思います。
ただ、これらは大きな要素ですが、必ずしもこれだけで決まる物ではありません。
上記5の消費者の求めるものという点も関わってきます。
どんなに高品質であっても、現実的な観点として現在の住宅事情に対し著しく大きい段飾りなどは需要が低くなるものです。お客さまや時代のニーズに沿っているかという点も大きな要素になります。
また、百貨店や有名店など販売ブランド力、店舗の維持費や接客スタッフの人件費、問屋の介在・仕入れ品の数量価格差、物流も違いの出るところになるでしょう。
昨今は社会全体に物価高が押し寄せているため大変世知辛いことで…メーカーであり、直販店運営をする弊社としても出来る限り安定した価格に抑えるよう日々努力をしております。